トップページ![]() 滝宮総合病院の活動
滝宮総合病院の活動

令和7年1月29日(木)19:00〜19:45、健康館5階講堂にて、インターネットを利用した認知症の診療に関する勉強会が開催され、多数のスタッフが参加しました。
アルツハイマー認知症とは、主に高齢者に発症する神経変性疾患です。脳内にアミロイドβタンパク質が異常に蓄積され、神経細胞の死滅や脳萎縮により、記憶喪失、認知機能の低下、行動の変化などの症状が現れます。
アルツハイマー認知症の初期評価は、医師が患者の症状を評価し、認知症の可能性があるかどうかを判断します。その後、身体検査や認知検査、画像診断、血液検査のステップを経て診断に至ります。
勉強会では、ここ数年で臨床での使用が進んでいる、アルツハイマー認知症患者の脳に蓄積された物質を測定するバイオマーカーという方法についての説明が行われました。また、認知症の治療に有効な薬剤や実際の症例など、幅広い事例が紹介されました。
今後も新しい医療知識の習得や技術の更なる研鑽に励み、良質で安全・安心な医療提供に努めてまいります。
令和7年1月16日(木)、患者さまの夕食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。
当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。
この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。
今回の献立は「米飯」、「鶏肉のガーリックソテー」、「野菜スープ」、「牛乳寒天」で、「米」、鶏肉のガーリックソテーの「とりもも肉」が県産品です。(県産品の使用率は50.7%となっています。)
とりもも肉に含まれるたんぱく質は、高品質で消化吸収が良いため、筋肉の維持や増強に役立ちます。特にリハビリ中の患者様や筋力を維持したい高齢者にとって有益です。また、たんぱく質は免疫細胞の生成にも必要です。十分なたんぱく質を摂取することで、体が感染症や病原菌に対する抵抗力を強化します。さらに、ガーリック(にんにく)には抗酸化物質であるアリシンが含まれており、体内で活性酸素を中和し、免疫力を高める効果が期待されます。
今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年1月16日(木)19:00〜19:20、健康館5階講堂にて、インターネットを利用しためまいの治療に関する勉強会が開催され、多数のスタッフが参加しました。
めまいは、不安が強く関係するものと、そこまで強く関与しないものの二つに分けられます。今回は、不安が強く関係するめまい、特に持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)とメニエール病について説明が行われました。
不安の感じ方には個人差がありますが、ホルモンの影響や社会的役割等から、女性の方が不安を感じやすく、また症状を訴えることも多い傾向にあります。強い不安がもとでめまいが発生し、そのめまいに対する不安や苛立ちから、さらなるめまいが発生する悪循環に陥りやすいことも確認されています。
勉強会では、その不安感を解消するのに有効な漢方を含めた薬剤が紹介されました。
今後も新しい医療知識の習得や技術の更なる研鑽に励み、良質で安全・安心な医療提供に努めてまいります。
令和7年1月10日(金)、香川県赤十字センター様にご協力いただき、当院東側駐車場にて献血を実施しました。
日本赤十字社によりますと、輸血用血液の在庫は不足し始めている地域が増えており、全国的にもこの状況が続いているそうです。特に、コロナ禍以降、献血協力者数が回復していないことから、深刻化しているとのことです。
今回の参加者は前回(令和6年2月28日)より3名減の25名でした(採血人数は23名でした)。
当院は、今後も献血活動に協力して参ります。
令和7年1月29日(水)15:00から開催の「院内学術講演会」のご案内です。
令和7年1月7日(火)、患者さまの昼食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。
当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。
この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。
今回の献立は「米飯」、「卵焼き」、「揚げ茄子の鶏味噌かけ」、「みかん」です。献立の中で「米」、卵焼きの「卵」、揚げ茄子の鶏味噌かけの「鶏ミンチ」、「みかん」が県産品です(県産品の使用率は54.6%となっています)。
また、1月7日は五節句のひとつ、「人日の節句」であり、「七草粥の日」です。古来中国では、この日に7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの=汁物)を食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草粥となりました。その一年の無病息災を願って1月7日の朝に食べるのが作法です。これに倣い、朝食には七草粥を提供しました。
今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。


1月6日、新年始業式を開催しました。式典には多くの職員が出席し、新しい年のスタートを祝いました。
式典では田宮理事長が職員の士気を高めるとともに、前向きな展望と明確な目標を示す挨拶を行いました。また、進藤副院長が挨拶を行い、今年度の目標や取り組みについて説明しました。
始業式は短いながらも意義深い時間となり、職員一同が新たな気持ちで一年をスタートさせる良い機会となりました。


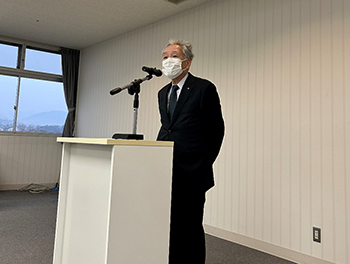
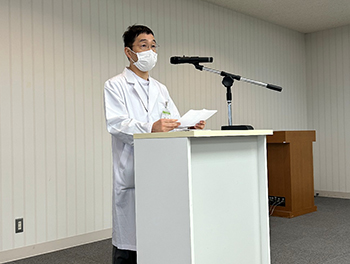
年末年始はゴールデンウィークやお盆と並び、いわゆる大型連休になりますが、病院には年末年始も多くの患者さまが入院し、病気やけがの治療のため病院で過ごされています。これらの患者さまに少しでもお正月の雰囲気を味わって頂きたく、年末年始らしいお食事を提供しました。
12月31日の夕食は「しっぽくそば」、「天ぷら盛り合わせ」、「みかん」です。「しっぽくそば」が「年越しそば」になります。
1月1日の朝食は「米飯」、「雑煮」、「田作り」、「こまつな煮浸し」、「牛乳」です。お雑煮の餅は残念ながら餡餅ではなく、のどに詰まる事の無いようムース状に加工したものを使用しました。
昼食は「赤飯」、「おせち(ぶり照り焼き・かずのこ・煮しめ・昆布巻・梅花くずし・鶏肉の野菜巻き・佃煮黒豆・だて巻き)」、「紅白なます」、「和菓子」を元日の行事食として提供しました。
古代より赤い色には邪気を祓う力があると考えられ、また米は価値の高い食べ物であったことから、神様に赤米を炊いて供える風習があったと考えられており、そこから災いを避ける、魔除けの意味で振る舞われるようになったそうです。
夕食は「米飯」、「ローストポーク」、「ほうれん草浸し」、「鯛吸い物」です。「鯛」は皆さまご存じのとおり「おめでたい」との語呂合わせも重なり、定番のメニューとなっています。
当院では、「地産地消食」だけではなく、季節を感じていただけるような食材・料理を献立に取り入れた「行事食」を毎月1回提供しています。
今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和6年11月26日から28日の3日間、近隣中学校の職場体験学習として、2年生の生徒2名を受け入れました。
病院で働いている職種について幅広く知ってもらうため、注射薬や飲み薬を扱う薬剤師、当院の特徴の一つであるPET-CT装置などを扱う診療放射線技師、血液検査のみならずエコーや心電図を扱う臨床検査技師、病棟や外来で幅広く患者様のケアを行う看護師、人工呼吸器はじめ生命維持装置を扱う臨床工学技士、病院で行っている講演会の受付事務の職場をそれぞれ体験・見学してもらいました。
体験された生徒さんからは「みなさんが患者さんを第一に思っていることを強く感じました」、「今回の経験を活かし、患者さんの立場に立って、どう接することが良いか考えて行動できる、優しい看護師になりたいです」とのお言葉を頂きました。
私たちは積極的な教育活動に取り組み、将来に向けた人材の育成に努めてまいります。

